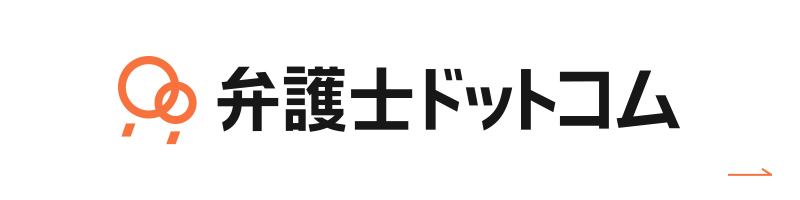遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“生前贈与を非課税で行う方法”に関する解説を行います。
非課税贈与の基本
生前贈与は相続税対策として有効な方法ですが、贈与税が課される可能性があります。しかし、適切な制度を利用することで、贈与税を抑えることが可能です。
基礎控除の活用
毎年110万円までの贈与については、基礎控除として非課税となります。この制度は受贈者ごとに適用されるため、計画的な資産移転が可能です。
住宅取得等の特例制度
住宅取得資金贈与の特例
直系尊属からの住宅取得資金の贈与については、最大1,000万円まで非課税となります。これは若い世代の住宅取得支援を目的とした制度です。
教育資金贈与の特例
30歳未満の子や孫への教育資金贈与は、1,500万円を限度に非課税となります。学費や教材費など、幅広い教育関連支出が対象となります。
結婚・子育て資金贈与の特例
18歳から49歳までの子や孫への結婚・子育て資金の贈与は、1,000万円まで非課税です。結婚式費用や子育て関連費用が対象となります。
夫婦間贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与については、2,000万円まで非課税となります。ただし、一生涯で一度限りの適用となります。
相続時精算課税制度
60歳以上の親から18歳以上の子への贈与で、2,500万円までの特別控除が適用されます。ただし、この制度を選択すると後で相続財産に合算されます。
効果的な活用のポイント
計画的な贈与
基礎控除を活用する場合は、毎年一定額の贈与を行うことで、長期的な資産移転が可能です。
特例の組み合わせ
複数の特例を組み合わせることで、より効果的な資産移転が可能となります。ただし、各制度の要件や期限には注意が必要です。
適切な活用には専門的な知識が必要

生前贈与の制度は複雑で、適切な活用には専門的な知識が必要です。当事務所では、お客様の状況に応じた最適な贈与方法をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。