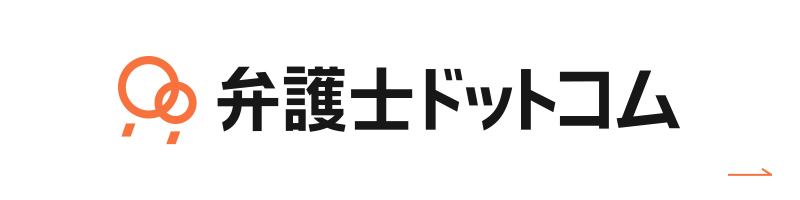遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“相続した土地の名義変更”に関する解説を行います。
相続登記の義務化について
2024年4月1日から、相続した土地の名義変更(相続登記)が義務化されることとなりました。これにより、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。これは法改正以前に相続が発生した土地についても適用されるため、早めの対応が望まれます。
名義変更の基本的な流れ
相続土地の名義変更には、以下のような手順が必要となります。
対象となる土地の特定
まずは相続対象となる土地の登記事項証明書を取得し、現在の権利関係を確認します。土地の所在地が不明確な場合は、市町村役場で名寄帳を取得することで特定が可能です。
必要書類の収集
相続登記には複数の書類が必要となります。具体的には被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や住民票などが必要です。また、固定資産税評価額を証明する書類も準備します。
遺言書の確認
遺言書の有無により必要な手続きが異なります。遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要となることがあります。
相続方法の決定
遺言書がない場合は、法定相続分での相続か、遺産分割協議による相続かを決定します。遺産分割協議を行う場合は、相続人全員の合意による遺産分割協議書の作成が必要です。
登記申請手続き
申請書類の作成と提出には細心の注意が必要です。特に以下の点に留意が必要です。
登録免許税の計算
固定資産税評価額をもとに登録免許税を計算します。一般的な相続登記の場合、評価額の0.4%となります。
書類の提出方法
法務局への提出方法には、窓口での直接提出、郵送、オンライン申請があります。初めての方は、事前に法務局の登記相談を利用することをお勧めします。
専門家への依頼

相続登記の手続きは複雑で、多くの書類や手続きが必要となります。特に以下のような場合は、専門家への依頼を検討することをお勧めします。
- 相続人が多数いる場合
- 被相続人の転籍回数が多い場合
- 遺産分割協議が必要な場合
- 時間的余裕がない場合
当事務所では、相続登記に関する相談を承っております。手続きの複雑さや時間的制約でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、皆様の状況に応じた最適なサポートを提供いたします。