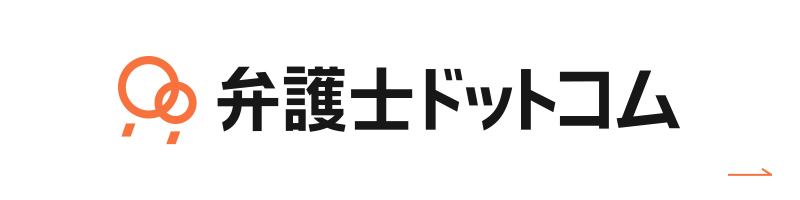遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“寄与分”に関する解説を行います。
寄与分制度の意義と概要
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人が、法定相続分に加えて受け取ることができる追加的な相続分のことを指します。この制度は、被相続人への貢献に対する適切な評価と、相続人間の実質的な公平を図ることを目的としています。
寄与分が認められる要件
寄与分が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 寄与行為が相続開始前に行われていること
- 被相続人の財産維持・増加に特別な貢献があったこと
- その貢献に対して十分な対価を得ていないこと
- 一定期間以上の継続的な貢献であること
寄与行為の具体的類型
寄与分が認められる代表的な行為には以下のものがあります。
- 家業従事型:被相続人の事業に無償で従事
- 療養看護型:被相続人の介護や看病
- 金銭等出資型:被相続人の事業や生活への資金提供
- 財産管理型:被相続人の財産の維持・管理
- 扶養型:被相続人の生活支援
寄与分の主張と立証
寄与分を実際に認めてもらうためには、適切な主張と証拠の提出が重要となります。
立証に必要な証拠
以下のような資料が証拠として重要となります。
- 介護記録や診断書
- 金銭支出の証明書類
- 事業への従事を証明する書類
- 第三者の証言
寄与分の算定方法
寄与分の具体的な金額は、以下の要素を考慮して決定されます。
- 寄与行為の期間と程度
- 寄与行為による財産の維持・増加の程度
- 他の相続人の貢献度との比較
- 被相続人の財産状況
寄与分を主張する際は専門家に相談を

寄与分の主張は、その性質上、他の相続人との間で争いとなりやすく、また立証が困難な場合も少なくありません。そのため、早い段階から専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
当事務所では、寄与分に関する相談を承っております。ご自身の貢献が適切に評価されるよう、経験豊富な弁護士が丁寧にサポートいたします。寄与分でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。