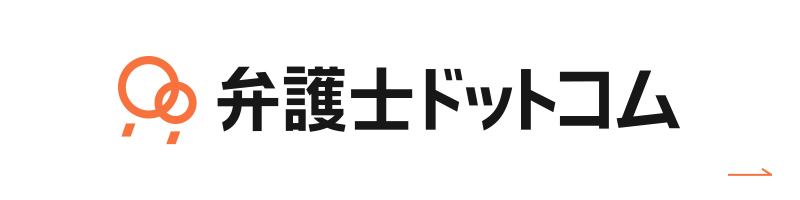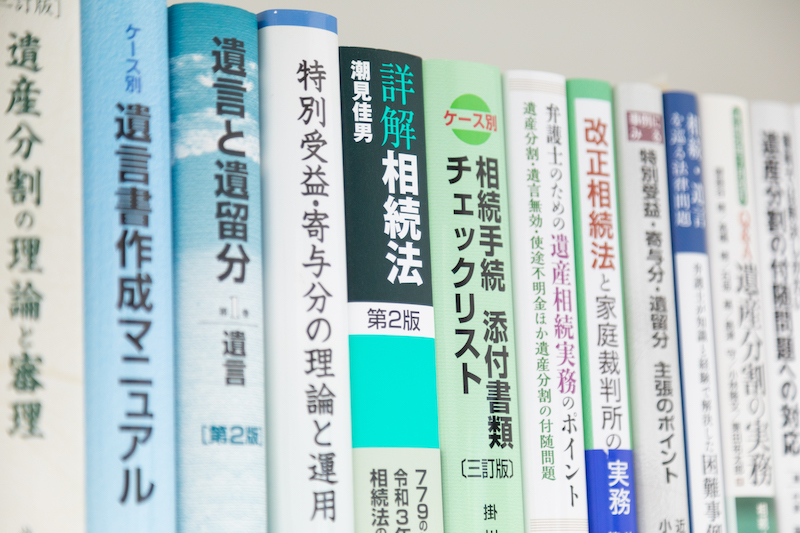
遺産相続は、理想的には家族の絆を深めるものであるべきですが、しばしば複雑な問題を引き起こします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、こちらのブログを通じて、皆様に相続に関する様々な疑問や問題に対処するための知識と解決策を提供します。相続の手続きの基礎から税金の問題、遺言書の作成方法に至るまで、遺産相続に関わる様々な知識・情報をお伝えして参ります。
今回のブログでは“預金相続手続きの流れ”に関する解説を行います。
相続開始時の基本的な流れ
銀行への死亡通知
被相続人の死亡後、まず必要となるのが金融機関への死亡通知です。通知後、該当口座は凍結され、通常の引き出しができなくなります。
必要書類の収集と準備
相続手続きには、以下の書類が必要となります。
- 被相続人の戸籍謄本及び除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書(必要な場合)
手続きの進め方
遺言がある場合
遺言書に基づく相続の場合、受遺者または遺言執行者が手続きを行います。公正証書遺言以外の場合は、検認手続きが必要となります。
検認は家庭裁判所で行われ、遺言書の形式や内容の確認が行われます。特に自筆証書遺言の場合は、遺言書の真正性を確保するため、この手続きが重要となります。検認完了後、検認調書または検認済証明書が発行され、これを金融機関に提出することになります。
遺産分割協議による場合
相続人全員の合意により遺産分割を行う場合は、協議書の作成と全員の署名・押印が必要です。協議書には分割する財産の特定と各相続人の取得分を明確に記載する必要があります。
また、印鑑証明書の添付が必要で、作成から3ヶ月以内のものを用意します。協議の内容は、法定相続分と異なる分割も可能ですが、遺留分を考慮する必要があります。
仮払い制度の活用
葬儀費用等の緊急の支払いに対応するため、一定額(150万円まで)の仮払い制度があります。この制度は、相続人が単独で申請できます。
具体的な引出し可能額は、預金残高の3分の1に法定相続分を乗じた額となります。申請には、相続人であることを証明する戸籍謄本等の書類が必要です。この制度は各金融機関で独自に設けられているため、具体的な手続きは機関によって異なる場合があります。
手続き上の注意点
早期対応の重要性
手続きに期限はありませんが、放置することでリスクが高まります。休眠口座化や不正利用の防止のため、速やかな対応が望ましいです。
相続放棄との関係
相続放棄を検討している場合は、預金の引き出しや解約を行わないよう注意が必要です。これらの行為は単純承認とみなされる可能性があります。
預金相続に関する相談を承っております

当事務所では、預金相続に関する相談を承っております。書類の準備から手続きまで、経験豊富な弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。手続きの煩雑さや相続人間の調整など、様々な課題に対して適切なアドバイスを提供いたします。